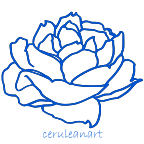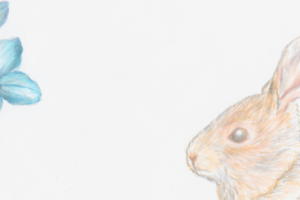1年の間に稼いだ収益、かかった費用を表す損益計算書(PL)💰
1時点での、企業の財産や借金の残高を表す貸借対照表(BS)👛
同じ企業の決算書であっても、対象とする期間も、表す項目もまったく異なるこの2つの書類には、実は切っても切れない関係があるのです。今回は、そんな損益計算書と貸借対照表の関係性について見ていきましょう✨
損益計算書の利益が貸借対照表の残高を変える
利益が出ると純資産が増える
毎年利益が出れば出るほど、貸借対照表の純資産の部の残高が増える、という関係があります。
なぜなら、期末の決算の度に企業側が当期純利益を集計し、その金額を純資産の部の「利益剰余金」(さらにその中の項目の「繰越利益剰余金」)に足していっているからなんですね😊
つまり、損益計算書で算出される各年の当期純利益が、貸借対照表の純資産の残高を構成しているのです。
当期純利益の詳しい解説はこちら(↓)
何が純資産を構成するの?
純資産の求め方は2つあります。
① 株主からの出資金(資本金と資本剰余金)+ 企業が今までに稼いだ利益の蓄積(利益剰余金)+ α (包括利益、少数株主持分など)
② 資産 - 負債
①を見ると、株主から出資を受けたり、利益が生ずることで純資産が増えることが分かります。
そうなると手元の現預金(資産)が増えますので、必然的に ②「 資産 - 負債 」の金額も増えることになります。
自らが稼いだ利益や株主から受けた出資金は、借金とは異なり、返済も利子の支払いも必要のない資金です。資金の回収に時間がかかる投資も、機動的に実行しやすくなります。
そのため、資金源を借金に頼っている企業よりも、純資産が潤沢にある企業の方が経営に安定感があるとも言えます✨
スポンサーリンク
利益の金額によってROEや自己資本比率が変わる
純資産の残高から一部の項目(少数株主持分、新株予約権)を除いた金額が「自己資本」です。
このように、純資産と自己資本は近い概念であるため、毎年の利益がいくらになるかによって自己資本の金額も変わるのです😲
そのため、1年間の利益が自己資本を使った指標(自己資本比率、固定長期適合率、ROEなど)を左右することになると言えます。
ROEの詳しい解説はこちら(↓)
マイナスの利益(赤字)と債務超過の関係とは?
債務超過はマイナスの利益から生み出される
債務超過を一言でいうと…
「資産 - 負債 < 0」の状態
=「純資産がマイナス」の状態
と、表せます😊
毎期の当期純利益が純資産に足されていくということは、言いかえると「マイナスの当期純利益(当期純損失)が出ると純資産が減ってしまう」ということです。
それが積み重なると、やがて純資産自体がマイナスの金額になってしまいます。
これは、「資産ー負債<0」、つまり財産すべてを使っても負債を支払えない債務超過の状態に陥ったことを意味します💦
債務超過=倒産ではないが…
債務超過に陥っても、手元に資金がある限りは事業を続けていくことはできます。
しかし、債務超過になるほど財政状態が悪化していると、銀行も資金の貸し出しには厳しい姿勢を示してくるでしょう。さらに債務超過の状態が1年を超えると、上場廃止にも追い込まれてしまいます。
ただでさえ資金が不足している状態なのに、借入や株式の発行によって新たに資金を調達することが難しくなってしまうのです😥取引先も経営状態の悪い企業と取引をしたがりません。
つまり、すぐに倒産とはならなくても、債務超過という事実が事業の運営にとってかなり厳しい環境を作ってしまうのです。
【事例:東芝】上場廃止の危機から見えた「損益計算書と貸借対照表のつながり」
では、具体的に赤字(当期純損失)がどのように純資産を動かしていくのか、2016年度の東芝の決算書を例に見ていきましょう🗝
2016年度の東芝の経営状況
会計不正の発覚をきっかけに、東芝は経営状態の悪さを露呈することになりました。
事業の売却により利益を底上げしようとしたものの、構造改革に多くの費用を使っていることに加え、2016年度には海外の原子力子会社が破産したことに関連する巨額の損失が発生しました。
そのため、東芝の損益計算書では3年連続(2014~2016年度)で当期純損失が出てしまったのです。
当期純損失が貸借対照表をどう変えたか?
ただでさえ激減していた純資産に追い打ちをかけたのは、2016年度の「当社株主に帰属する当期純損失」-9656億円という巨額の赤字。
この金額がそのまま足し込まれた2016年度末の東芝の純資産の部(※)は、2015年度末と比べて9479億円減ってしまいました。(※東芝は米国会計基準を採用しているので、実際の表記は「資本の部」となっています)
結果、2016年度末の純資産の部は-2757億円と、マイナスの数値に食い込んでしまったのです😰つまり、債務超過の状態になったのです。
これを資産・負債側から見てみると、現預金や投資有価証券の減少により資産が大きく減少している一方で、負債側は債務保証損失引当金(※)が増えたことなどにより、借金を返済しても残高をあまり減らすことができていませんでした。(※海外の原子力子会社が破産したことにより、東芝が今後支払わなくてはならない原子炉建設プロジェクトの保証額を引き当てたもの)
そのため、「資産 < 負債」という構図になってしまったのです。
債務超過脱却に向けた東芝の作戦
2017年度末においても債務超過の状態が続いていると、上場廃止に追い込まれてしまいます。
なんとかして上場廃止を阻止するべく、東芝は純資産の部(資本の部)を増やし債務超過から脱却する作戦を考えました。
案1:損益計算書と貸借対照表のつながりを生かす方法
当初の有力案は、東芝の中でも成績優良なメモリ事業を売却することです。そこから得た売却益で当期純利益をかさ上げすれば、当期純利益が組み込まれた後の純資産を大幅に増やすことができます。
しかし、メモリ事業の売却先には目途がついたものの、果たして年度末までに売却の手続きが完了できるかについては段々と不透明な状況になっていきました。
そこで、東芝は別の策も考えたののです。
案2:ダイレクトに純資産を増やす方法
その代替案とは、資本金を増やすことです。利益剰余金を大きく増やせなくても、資本金を増やすことで純資産(資本の部)の残高を押し上げることができます。
東芝は国内・海外の投資家を対象に増資の引き受け先を探し、結果、2017年度末までに6000億円規模の出資を受けることに成功しました(この時の出資者が物言う株主であったことで、後日大規模な株主還元が行われます)。
残された少ない時間の中で数千億円単位の金額を動かさなくてはならなかったため、いずれも東芝が痛みを伴う作戦であったと言えます。
(翌年度に案1の作戦も決行されています)
スポンサーリンク