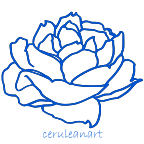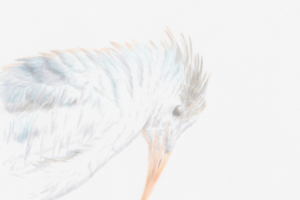2017年6月についに経営破綻したタカタ。エアバッグの不具合が露呈してから、すでに10年以上の月日が経っていました。
エアバッグ問題発覚後、長い時間をやり過ごしてきたタカタは、なぜ2017年に経営破綻という結論を導いたのでしょうか?
今回は、いくつかの方法でタカタの決算書を経営分析しながら、倒産の原因をひも解いてみます🗝
実は向上していた収益性
まず、エアバッグ問題がタカタの本業の収益性にどのように影響したのかを、営業利益率を使って探ってみましょう。
営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上高
営業利益率の詳しい解説はこちら(↓)
営業利益率の変化を見てみよう
経営破綻前5年間のタカタの営業利益率を見てみます。
2013年3月期 → 3.5%
2015年3月期 → 5.1%
2017年3月期 → 5.9%
悪化するどころか、むしろ営業利益率は上がっています。
実は本業は好調だった!?
実はこの5年間、売上高も増える傾向にありました。最後の2017年3月期こそ、売上高は少し落ち込んだものの、営業利益率は上昇しています。
エアバッグの問題により、タカタの信頼性は揺らいだに違いありません。それでもタカタの高い技術力ゆえ、自動車メーカーもタカタの代わりを見つけることが難しいのでしょう。
エアバッグ問題に引きずり落とされない収益性は、自動車業界におけるタカタの存在感の大きさを物語っています。
スポンサーリンク
タカタの資金力には変化が生じていた
では、今度はタカタの資金力の面から分析してみましょう。自己資本比率、固定比率、流動比率の3つの指標を使っていきます😊
ガクンと落ち込んだ自己資本比率
まず、タカタの自己資本比率に着目してみましょう✨自己資本比率は、企業が事業に使っている資金のうち、返済する必要のない資金(=自己資本)の割合を表します。
自己資本比率 = 自己資本 ÷(負債 + 自己資本)
自己資本比率の詳しい解説はこちら(↓)
自己資本比率の変化を見てみよう
ここ5年間のタカタの自己資本比率には変化が見られました。
2013年3月期 → 39.5%
2015年3月期 → 31.0%
2017年3月期 → 7.0%
緩やかに下降していった後、最後の1年でガクンと落ち込んでいます。
自己資本比率を押し下げた原因
最も大きな原因は、エアバッグ問題に関連して巨額の訴訟費用や罰金等が計上されたために赤字が続いた(特に2017年3月期は大幅な赤字)ことです。これにより、5年間で自己資本は5分の1の金額になってしまいました。
つまり、返済が不要な資金が目減りしてしまったのです。
自己資本の構成要素の1つに「今までの利益の蓄積」があるため、赤字になるとこの部分が減ってしまうんですね。
自己資本比率が落ち込んだもう1つの原因は、負債が増加したことです。
実は、負債の増加の理由は借金が増えたことではないんですね。ここがタカタ破たんのカギを握るポイントでもあるのですが、この理由については後ほど解き明かしていきます🗝
自己資本比率7%が意味することとは?
自己資本比率の低下は、返済する必要のない資金の割合が減ってしまっていることを表します。
2017年3月期の自己資本比率7.0%という数値は、事業に使う資金の殆どが、今後流出していく資金によりまかなわれている状態を示しています。「安定して事業を継続できるか?」という点において、危険信号が灯っていたのです。
100%を大幅に飛び越えた固定比率
次に使う指標は、固定比率です。固定比率は、投資を行った後も支払いを乗り切って活動を続ける力を表します。
固定比率 = 固定資産 ÷ 自己資本
固定比率の詳しい解説はこちら(↓)
固定比率の変化を見てみよう
では、経営破綻前5年間の固定比率の動きを見てみましょう。
理想は、投資に必要な金額を返済不要な資金である自己資本でまかなうことです。これは、固定比率が100%以下の状態です。
2013年3月期 → 80.4%
2015年3月期 → 110.0%
2017年3月期 → 370.1%
経営破綻から5年前の2013年3月期は、固定比率が100%を下回ることができていますね。
そこから徐々に固定比率が上昇し、経営破綻直前の2017年3月期は100%を大きく上回った状態(370.1%)となってしまいました。
固定比率の急上昇が意味すること
これは、固定資産(=今まで投資した金額を表す)のうち、返済不要な資金でまかなえているのが3割にも満たない状態であったことを表しています。
つまり、残りの7割強は、いずれは流出していく資金でまかなっているのです。設備投資等のリターンを十分に得る前に、借金等の債務の支払いに行き詰まるリスクが高い状態とも言えます。
自己資本比率が低下した原因と同じく、赤字が続き自己資本が縮小したことが固定比率を押し下げていました。
危険水域に突入した流動比率
タカタの資金力面の分析として、最後に流動比率を見てみましょう⭐流動比率は、「今日明日の目先の支払いを行う力があるか?」という短期的な支払い能力を測るときに使います。
流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
流動比率の詳しい解説はこちら(↓)
流動比率の変化を見てみよう
流動比率の理想は200%です。100%を下回ると、「1年以内にお金に変わる金額< 1年以内に支払う義務のある金額」という企業の状態を示します。
2013年3月期 → 172.4%
2015年3月期 → 134.9%
2017年3月期 → 93.6%
流動比率は徐々に下がりつつも、2016年3月期までは何とか100%を上回っていました。しかし、2017年3月期において、あることが原因で流動比率が100%を切ってしまったのです。
流動比率が100%を切った原因とは?
その原因とは、エアバッグ問題に関連して、アメリカの司法省との合意により自動車メーカーのための補償基金への拠出が決まったことです。この合意があった2017年3月期において、将来の拠出が決まった953億円が「未払金」として流動負債に加わりました。
そのため、2017年3月期の1年間だけで流動負債が1.5倍近くに膨らみ、流動比率の100%割れが引き起こされたのです。
米国司法省との合意が自己資本比率に影響を及ぼした
953億円の「未払金」の登場によって、タカタの負債は急激に増えました。これが、先ほどご紹介した、自己資本比率を押し下げたもう1つの要因でもあります。
アメリカの司法省との合意によって、1000億円近くの資金が近々行われる補償基金への拠出用に拘束されてしまったのです😭
タカタが直面していた危険とは
通常、流動比率が100%を下回っても、事業が順調に回り続けているうちは何とか乗り切っていけるかもしれません。
しかし、タカタの場合、ただでさえ訴訟関係でキャッシュが流出しているうえ、今後は自動車メーカーからリコール費用を請求されることが火を見るよりも明らかです(この時点では、自動車メーカーとのリコール費用の負担割合が不明であることを理由に、債務として認識していません)。
たとえ事業は順調に回っても、事業以外のところで巨額の支出が見込まれるため、そう遠くないうちに資金が底をついてしまうことは容易に予見できました。信頼性がグッと下がった今のタカタでは、銀行から借り入れを行うのも至難の業でしょう。
このような状況の中、流動比率が100%を割っている状態では、「すべての流動資産をお金に変えても、1年以内に支払うべきお金をまかなうことができない」のです。支払いができなくなるとは、つまりは倒産を意味します。
スポンサーリンク
まとめ~タカタの倒産の原因とは?
1.タカタへの信頼性は揺らいだものの、事業の収益性は上がっていた。
2.エアバッグ問題に関連して訴訟費用や罰金等の費用がかさみ、返済の必要がない資金力が落ちていた。
3.経営破綻直前の2017年3月期には、1000億円近くの資金が近々補償基金へ拠出されることが決まった。つまり、この時点でタカタの事業に使う資金の大半が今後流出する資金でまかなわれていたことになる。
4.今後もエアバッグ問題に関連した支出が見込まれており、このままいけば資金が底を尽くことが目に見えていた。
エアバッグで問題が発生した後も、その技術力とシェアの高さゆえ、タカタの本業自体には大きな影響が無かったのかもしれません。しかし、資金面では確実に窮地に追い込まれていきました。
さらには今後も多額の支出が見込まれており、2017年3月期時点のタカタは資金ショートに向かって突っ走っていた状態だったのです。
タカタの事業が停止すれば、自動車業界に大きなダメージを与えます。資金ショートとなる前に、民事再生法を適用し、健全な事業については存続させる道を用意したのです。