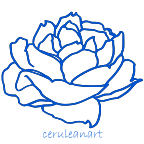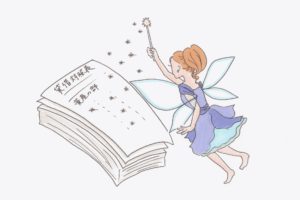売上原価の計算式はシンプルであるものの、それだけ見ると「???」となる方も多いのではないでしょうか?😊
「売上原価とは何?」という所がわかれば、計算式の意味も分かりやすくなります。
まずは、売上原価の意味を学びながら、その求め方をひも解いていきましょう!
そもそも売上原価とは何?
損益計算書の中でも、一番最初に出てくる費用が売上原価です。
売上原価とは、その年に販売された商品の仕入金額・製造金額のことです。
この「その年に販売された」という所がポイントです!
その年に仕入れた費用であっても、売れ残ってしまった場合は売上原価には含まれません。もし1つも商品が売れなかったら、その年の売上原価は0になってしまうのです。
仕入れと売上原価の違いについては、こちらで詳しく解説しています(↓)
なぜ、商品を仕入れたタイミングではなく、販売されたタイミングで売上原価が計上されるのか、その理由をご説明しますね😊
売上原価は費用の中でも特別な扱い
通常、費用は対象となるモノやサービスを使ったときに生じます。
たとえば切手を買った場合、その費用は買ったときではなく、手紙に貼って使ったときに発生します。
費用は、この発生の時点で計上します。
(※これを発生主義と呼びます。)
このうち、売上高に直接結びつけられる費用に限っては、対応する売上高が上がったときに計上することになっています。
売上高に直接結びつけられる費用とは、売上原価のことです!売上原価は商品ごとの金額を把握できるので、どの商品が販売された分(=売上高が上がった分)なのか区別できますよね😊
たとえば、商品を作るためにアルミ板(材料)を使うとします。
このアルミ板の費用を計上するのは、商品を作るために使ったときではありません。そのアルミ板を使って作った商品が売れた時(=対応する売上高が上がったとき)に計上されるのです。
(※これを費用収益対応の原則と呼びます。)
つまり、売上原価を計算するためには、販売された商品の仕入金額や製造金額を求めればいいのです😊
スポンサーリンク
簡単な例で考えてみよう~高級時計店の例~
高級時計店を例に、売上原価の計算方法を考えてみましょう⌚
こちらの時計店では、1つ100万円の高額な時計を取り扱っております✨
開店1年目の売上原価
お店を開いて1年目、1個100万円の時計を5つ仕入れました。そのうち、売れた時計は3つです。
この年の売上原価を求めるには、売れた時計の仕入金額を合計すればいいので…
100万円 × 3(売れた数)= 300万円
となります。
販売された3つの時計の仕入金額が売上原価に、売れ残った2つの時計の仕入金額は棚卸資産(在庫)として貸借対照表の資産になります。
開店2年目の売上原価
2年目は、1個200万円の時計を6つ仕入れました。この年に売れた時計は、1年目に仕入れた100万円の時計2つと、2年目に仕入れた200万円の時計4つです。
この年の売上原価、つまり売れた時計の仕入金額は…
100万円 × 2 + 200万円 × 4 = 1000万円
つまり、昨年の売れ残りのうち今年売れた時計と今年仕入れて今年売れた時計の仕入金額が売上原価になるんですね。
そして、ここからがポイントです!
売上原価の別の計算の仕方として、
100万円 × 2(昨年の売れ残り)+ 200万円 × 6(今年仕入れた分)- 200万円 × 2(今年の売れ残り)=1000万円
のように、仕入金額全体から売れ残り分を差し引くことで、間接的に今年販売された時計の仕入金額(つまり売上原価)を求める方法もあります。
実は、売上原価の求め方としては、こちらの方法が一般的です😊
この計算方法が、多くの本やサイトでどのように紹介されているか、次のパートでお話します。
スポンサーリンク
売上原価の計算式を見てみよう
ここで、一般的に使われている売上原価の公式を見てみましょう!
売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 - 期末商品棚卸高
「棚卸高」とは、売れ残り商品の金額(つまり在庫の金額)のことです。この公式を言いかえると…
売上原価 = 前期の売れ残り商品の仕入額 + 当期の仕入額 - 当期の売れ残り商品の仕入額
ということになります😊
実はこれ、前のパート「簡単な例で考えてみよう~高級時計店の例~」の「開店2年目の売上原価」に出てくる2番目の計算式と同じ計算方法なのです。
公式を見ると漢字ばかりで「ぐぬぬ…」と感じますが、要するに、その年に売れた商品の仕入金額を計算しているんですね。
スポンサーリンク
まとめ
1.売上原価とは、その年に販売された商品の仕入金額・製造金額のことである。
2.売上原価は、対応する売上高があがったタイミングで計上される。その年に仕入れた商品であっても、販売されていなければ売上原価にはならず、棚卸資産に含められる。
3.売上原価を計算するためには、その年に販売された商品の仕入金額や製造金額を求めればよい。一般的には、「前年の売れ残り額 + 当期の仕入額 ー 当期の売れ残り額」の計算式によって、間接的に売上原価を求めることが多い。
今回は、売上原価を求める一般的な方法について解説しました。実は、製造業の売上原価を求めるには、これをさらにレベルアップした方法を用いる必要があります。
製造業の売上原価を求める方法については、こちら(↓)で解説しています😊